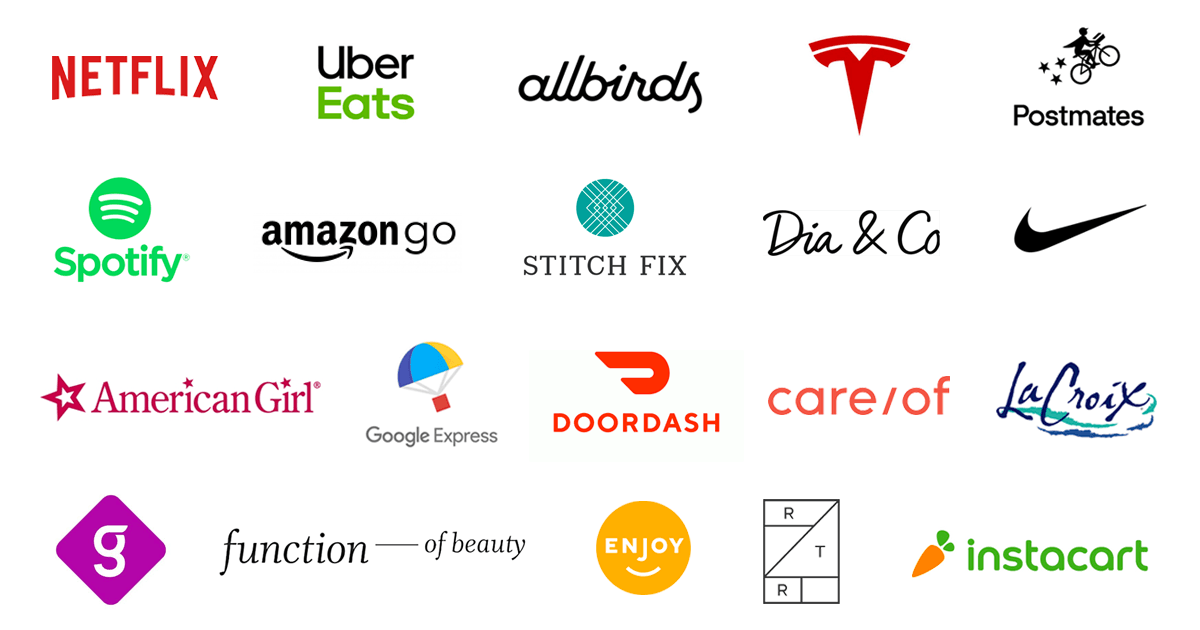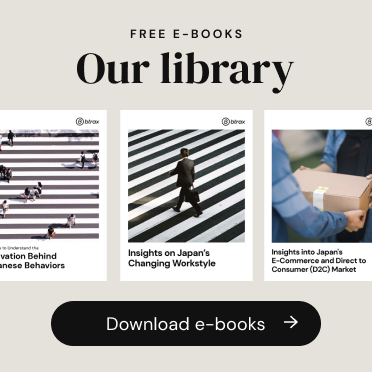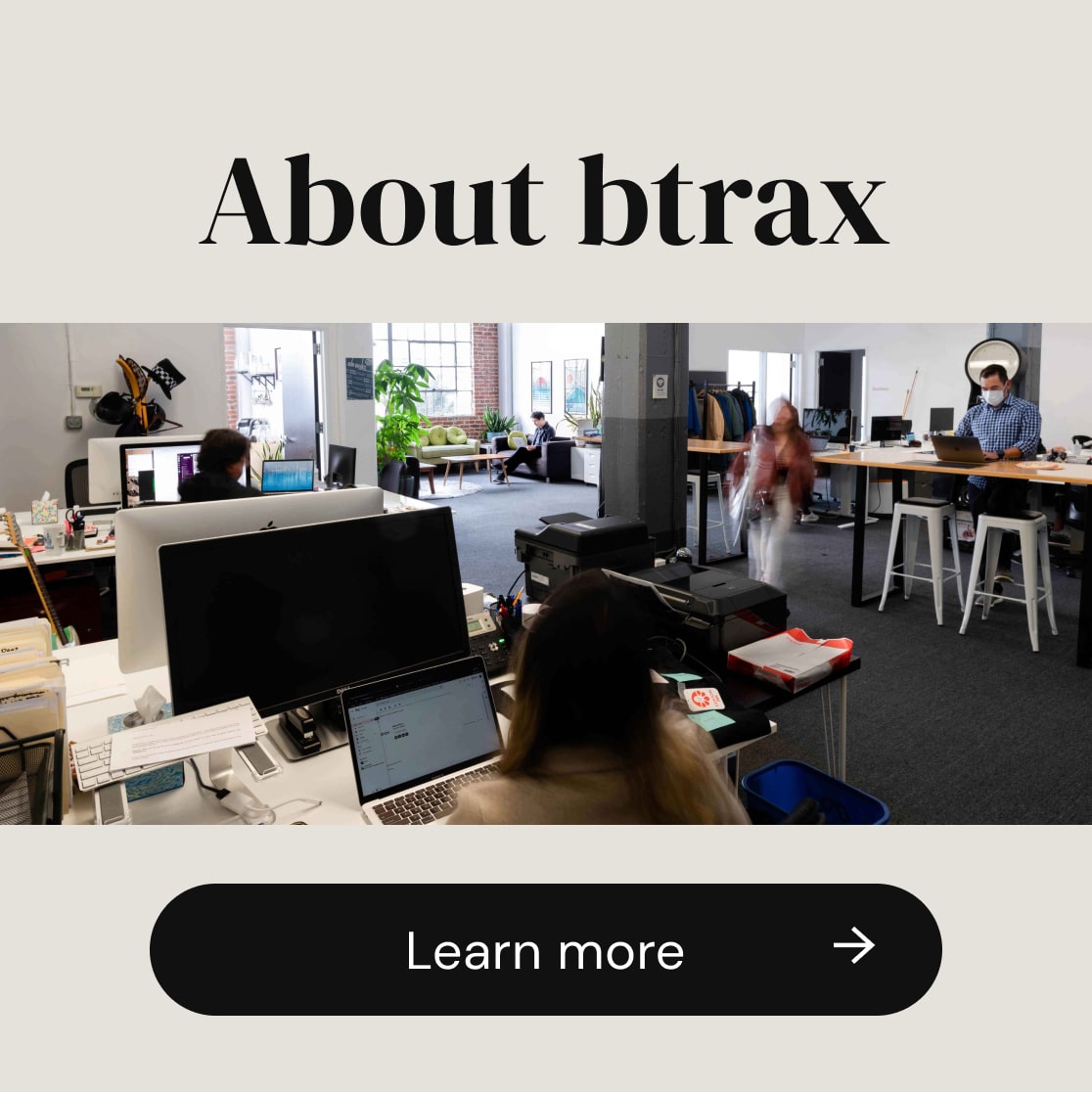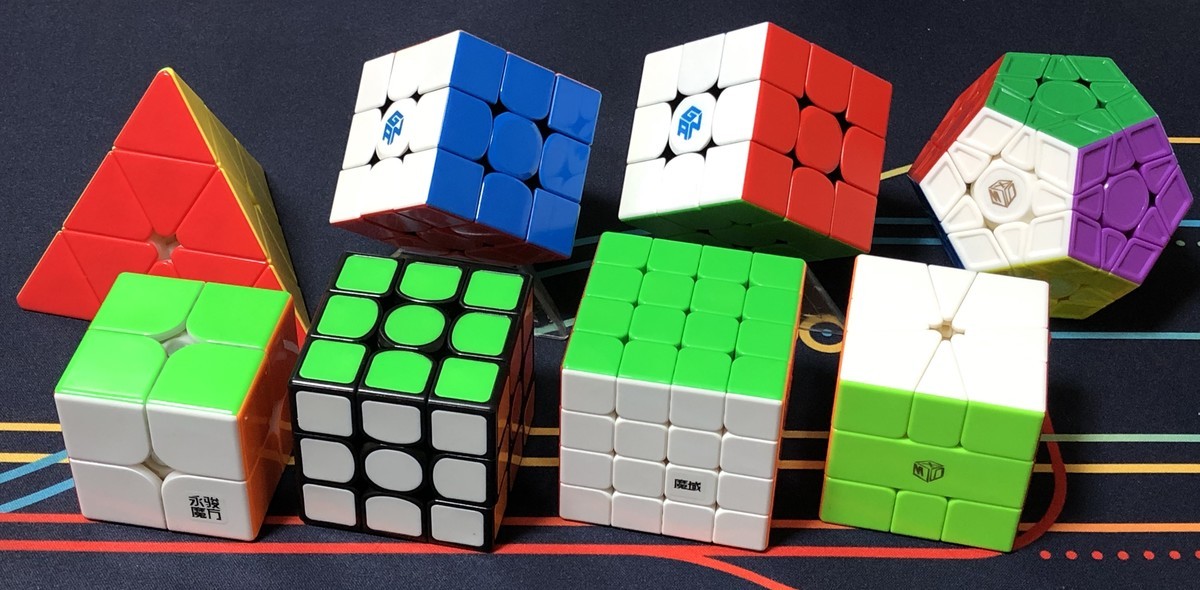
Btrax Design Company > Freshtrax > Japan marketing...
Japan marketing case studies
http://www.jma2-jp.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=524:201504217&catid=36:latest-topics
「LINE Creators Market」によるユーザーとの共創ビジネス (LINE㈱)
受賞理由:ユーザーとのCo-Creationによるビジネスの成功
スマートフォンコミュニケーションアプリ「LINE」内でのコミュニケーションアイテムである「スタンプ」の制作を公募してユーザーの制作意欲と功名心を刺激し、現在、8万種類以上のユニークなスタンプが販売されています。これによって企業とユーザーがともに利益を得るビジネスモデルを実現させ、ユーザーとのCo-Creationによる事業の最も成功した事例となりました。消費者のプロシューマー化を上手く捉えて新しいビジネスを生み出した企画力、LINEのプラットフォーム上で実現させた独自性、大きな社会的ムーブメントを引き起こした実績など、高い評価を受けました。
次世代4WINビジネスモデル、RBCおきなわ健康長寿プロジェクト「歩くーぽん」
(琉球放送㈱)
受賞理由:社会課題解決ビジネスモデルの開発
沖縄県民の健康意識を高めるために、歩くだけでファミリーマートのコーヒーなどが無料でもらえる万歩計アプリ『歩くーぽん』を開発し、テレビを使って積極的なプロモートを行いました。県民の30人にひとりがダウンロードするなど大きな反響を呼び、沖縄県民がこのアプリを使って記録した歩数は13億歩に達するなど健康維持に貢献。一方でファミリーマートの集客にもつながりました。スマホとテレビメディアを活用して社会課題解決をめざす、放送局と流通(コンビニ)によるソーシャルマーケティングの好事例です。
ファミリーマートは、Twitterでおむすびのアイデアを募集する「みんなで作るおむすび選手権」を開催した。想定をはるかに超える応募数、投票数を得て、商品3点を発売。テレビでも話題になり売れ行きは好調だ。2009年12月から公式Twitterを開設して、ファミマファンと交流してきた下地があってこその盛況といえる。
●ファミリーマート 【商品開発】
コンビニ業界で実現したTwitterを活用した初の商品開発の取り組み。普段、何気なく使っているコンビニだけに、実際に購入した人も多いかもしれません。
Twitterという開けた場を使い、消費者を巻き込み、情報を拡散させて話題を作りながら、この取り組み自体を一種のプロモーションキャンペーンとし、成功した事例です。
過去3回実施され、2013年にも4回目の「みんなで作るおむすび選手権」が開かれています。
※「みんなで作るおむすび選手権」の公式ページ、解説記事はコチラ↓
http://www.family.co.jp/campaign/omusubi2013/
http://japan.internet.com/wmnews/20100906/8.html
●ナイキ 【プロモーション】
ミクシィは、5月31日から21日間にわたって「NIKEiD FRIEND STUDIO」キャンペーンを展開し、ソーシャルグラフと既存のバナー広告をかけあわせた「ソーシャルバナー広告」の本格導入を試みた。
「NIKEiD」は、お気に入りのシューズやバッグなどを、自由にカスタマイズできるサービス。今回のキャンペーンでは、ユーザーは、mixi上に用意されたツールを使って、自分自身のオリジナルiD(商品)をデザインしてキャンペーンに参加する。また、「mixiチェック」を使い、友人へデザインを共有したり、自分がデザインしたiDを表示させるオリジナルバナーを作成することができる。
ソーシャルメディアの中で企業が広告展開をする上では、ソーシャルメディア内のソーシャルグラフを生かすことが有効であることが証明された事例です。
最終的に、mixi内のキャンペーンサイトを訪れたユニークユーザー数は213万人となり、一般的なバナーと比べて、PCではCTRが約11倍、モバイルでは約16倍となりました。
※「NIKEiD FRIEND STUDIO」の取り組みについて、もっと詳しく知るための記事はコチラ↓
http://markezine.jp/article/detail/14149
●花王 【プロモーション】
花王が、特定保健用食品(トクホ)「ヘルシア」シリーズのキャンペーンとして昨秋実施した「12週間健康チャレンジ」。運動やへルシアの飲用を日々記録して、TwitterやFacebookで仲間と励まし合う、このキャンペーンには1万7000人以上が参加した。期間中は、ヘルシアの売り上げが伸びる効果も見られ、ソーシャルメディアを絡めた販売促進の新たな可能性を示した。自信をつけた花王は今春、規模を拡大したキャンペーン第2弾を実施して、一層のヘルシア売り上げ増加を目指す。
ソーシャルメディアでは自分のがんばったことを書き込むユーザーが多く、見栄もあるのか、1度書くと継続していることをアピールするため、その後も挫折せずに継続的に取り組むモチベーションがわいてきます。
花王が「ヘルシア」で実施したキャンペーンはまさにそれ。挫折しがちなダイエット(=ヘルシアの継続飲用)の継続状況をソーシャルメディアで情報発信させることで、「3日坊主と思われたくない」という考えを持たせ、続けようとする意欲を持たせることに成功しました。
※花王「12週間健康チャレンジ」の取り組み、および花王のマーケティング戦略について、もっと詳しく知るための記事はコチラ↓
http://special.nikkeibp.co.jp/as/digitalmarketing/vol1.html
http://matome.naver.jp/odai/2136892790727292201?&page=2